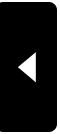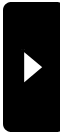2017年01月04日00:00
土づくり
カテゴリー │土づくり
2020年12月27日
空いたジャガイモと黒豆の場所を利用して、いただいたもみ殻堆肥づくりをした。太めで深めの溝を掘り下から落ち葉、もみ殻、米ぬか、もみ殻、バーク堆肥、発酵牛糞、もみ殻、油かす、コーランネオ、もみ殻を溝に入れて積層構造で、水やり。全部で10層以上は重ねたと思う。最後に、土を戻して鎮圧のため踏み固める。これが大事。全体重をかけると、かなり沈む。雨が降った後に、黒マルチをかける予定。昨年まではコンポスト容器でやっていた作業だが今年は籾殻の量と畑の空き具合から、容器は止めて、土の中で発酵させることにした。籾殻はそのままでは肥料にならず、発酵させる必要がある。
2020年11月8日
今日友人から藁と籾殻1袋をいただいた。毎年恒例のもみ殻堆肥づくりをする予定。今は場所が無いので、このままの状態で保留継続。

2020年1月25日
今日白菜が片付いたので、畝を使ったもみ殻堆肥づくりをした。もみ羅、鶏糞、米ぬか、落ち葉、白菜の残菜、コーランネオ半袋を順に重ねて、水やりして土を戻してしっかり鎮圧した。土を肥やすのと、籾殻を土になじませるのが目的。コンポスト容器も同じ。本当は1年くらい置きたいが、狭い畑では、そうはいかない。

2019年12月15日
一番南側のキャベツが片付いたので、2回目のもみ殻堆肥づくり。先週と同様に溝を掘り、もみ羅、鶏糞、米ぬか、油かす、キャベツの残菜、コーランネオ半袋を混ぜて、最後にたっぷり水やりして土を戻してしっかり鎮圧した。

2019年12月7日
容器が一杯だから、土の溝を利用して、もみ殻堆肥づくりを。一番北側の黒豆の収穫後、太め深めの溝を掘り下から落ち葉、もみ殻、米ぬか、わら、発酵鶏糞、油かす、コーランネオを畝全体に入れて混ぜて、水やり。まるで残渣ゴミの詰め合わせ。その後、土で蓋をして鎮圧のため何度も往復して踏み固める。これが大事。全体重をかけると、かなり沈む。このままでは作物が倒れるわけだ。雨が降った後に、黒マルチをかける予定。来年の春までに発酵した籾殻ができる?

2019年11月20日
水を追加。中の温度が上がっているようだ。発酵の兆候か?重石を3つほど入れた。1ヶ月くらいは放置の予定。
2019年11月16日
もみ殻堆肥発酵に「コーランネオ」という発酵促進剤を購入したので、もう一つのコンポスト容器もやる事にした。下の土を鍬で柔らかく耕した。その上に
もみ殻、発酵鶏糞、もみ殻、米ぬか、コーランネオ、もみ殻、油かす、コーランネオ、もみ殻、土の順で積み上げた。途中で水を大量に入れ、靴の裏で圧縮した。結構体積が下がる。さらに同じ事を繰り返す。途中黒大豆の枯れ葉も投入。コーランネオの採用も初めてだが、靴で圧縮したのは発酵に効果がありそう。
2019年11月10日
コンポスト容器を使ってのもみ殻堆肥発酵に一つだけ挑む事にした。下からもみ殻、発酵鶏糞、もみ殻、米ぬか、もみ殻、発酵牛糞を2回通り入れて水を多めにかけて終了。今年は初めて「発酵促進剤」なるものを使うことにした。「コーランネオ」という商品をジャンボエンチョーで購入。すでに階層を積み上げた後なので、スコップで掘りながら途中に入れた。最上部にも全体にまぶして、最後に土をかぶせた。はじめから使えば良かった。上手に発酵するかは、これからのお楽しみ。


2019年11月2日
同級生の農家さんから藁ともみ殻をいただいた。藁は来年の4月仕込みの春夏野菜につかう。もみ殻は、今年の秋冬野菜が終わる年明け早々に、空いた畝を使い発酵堆肥を作る予定。毎年コンポスト容器を使っているが今年は畑の畝を使う予定。もみ殻だけでも地質改良になるのだが、4ヶ月発酵させると立派な堆肥になる。

2019年4月21日
夏野菜に向けて、土づくりをした。先週、牛糞堆肥、油かす、米ぬか等を蒔いて耕した。今週は、石灰を蒔いて酸性度を中和した。先輩農家から苦土石灰より有機カキ殻石灰がいいと聞いたので、はじめて使ってみた。苦土よりやや多い量を蒔いた。20kg入りしかなかったので、かなり余ってしまった。使用量の目安は、4×5メートルの面積に約2Kgくらいなので、10分の1しか使わない計算だ。2週間後の5月4日ごろに夏野菜を仕込む予定。
また石灰購入でジャンボエンチョー染地台店に行ったら、連作障害防止の「菌の黒汁」入りのバーク堆肥を見つけたので思わず3袋も買ってしまった。1袋約500円。一緒に蒔いて耕した。苦い経験があるので、連作障害防止の文句にはめっぽう弱い。

2019年3月31日
キャベツ・ブロッコリーが終了し、北側端の玉ねぎと南側端の春ジャガ以外はすべて空いたので、コンポスト容器で作った籾殻堆肥をすき込んだ。容器一個分ではやや足りないので、残りは2個目の一部を来週作業する予定。さらに残りは、今の玉ねぎが終わったらすき込む予定。
今年の反省点として、水が少ない、攪拌ができていないため、牛糞堆肥や米ぬかが固まってしまった。来年からは土の下に入れて発酵させようと思う。牛糞堆肥とバーク堆肥で籾殻をサンドする方法がいいようだ。
2018年12月2日
籾殻堆肥を使った土壌改良(その2)を施した。容器がもうないので、空いた畝を使って同様の効果を狙う。黒豆が予定より早く空いたので、その畝2列に溝を深く掘り、そこに下から籾殻、発酵鶏糞、籾殻、米ぬか、油かす、籾殻、鶏糞、米ぬかと重ねた。途中で水を加え、土を被せた跡は何回も踏み土をしながら畝を往復した。それぞれが密着するように、圧縮した。コンポスト容器の時は、2個で籾殻1袋を使い切ったが、今回はけっこう余った。今週は雨が多そうなので、ちょうどいい。このまま4月下旬まで放置(土中では籾殻の発酵がすすみ堆肥として熟成されるはず)し、その後他の場所へ籾殻を振り分け、すき込む。

2018年11月18日
コンポスト容器を使った土壌改良に今年も挑戦してみることに。籾殻主体の完熟堆肥をつくって春夏野菜の仕込みの前(4月頃)に畑全体にすき込む予定。容器にサンドイッチ状に層を作って発酵・熟成・堆肥化を待つ。下から籾殻、発酵鶏糞、籾殻、米ぬか、油かす、籾殻、米ぬか、鶏糞、籾殻、腐葉土、籾殻、油かすと重ねた。2層くらい積み上げて足で踏んで圧縮し、水をかけての繰り返し。発酵促進剤は使わず、発酵剤は米ぬかや鶏糞に担ってもらう考えだ。約半年後には、完熟堆肥が完成。毎年、これを繰り返していけば、粘土質からの土壌改良にも役立つだろう。籾殻は水の通りがいいので排水性も高いはずだ。容器だけでは籾殻が半分以上余るので、空いた畑を掘り、その穴に同じように積み重ねて最後に土と水をかけて半年置いて熟成を待つ。

2018年10月6日
じゃがいも、大根といった冬野菜の準備中に粘土質の層を発見して、その修復作業にかなりの時間と費用を費やした。ひたすら黄茶色の粘土質の土を取り除き、その分の補充として「矢作砂(中粒)」とかバーク堆肥とかを入れた。矢作砂はこれまで合計10袋くらい買っているんじゃないかな?キャベツ、じゃがいも、大根の一部に使っている。今日も大根の土づくりの途中でまた出てきたので、削除と補充で明け暮れた。

2018年9月2日
夏野菜を片付けた。豪雨のたびに雨水が池のように貯まる西側の真ん中部分を掘りこんだ。案の定、途中から粘土質の黄茶の土が出てきた。粘土土を取り除いて減った分「パーライト」という黒曜石を補充する水はけ改良作戦を決行。掘っては取り除く作業を延々と決行。それが3カ所ほどあり、かなりの粘土土を取り除いた。といっても全体からすればごくわずか。パーライトが足らなくなったので、増し土2袋を購入(1袋25リットル/1袋400円ケーヨーD2)。
これで水はけがどの程度変わるか、まずは様子をみよう。

2018年5月27日
2つめのコンポスト容器で作った籾殻堆肥を、玉ねぎの収穫後にすき込んだ。
また、南側の畝の西側は排水が特に悪く、大雨の次の日には池ができる状態だ。地下の粘土質の土が原因と思う。地下の粘土質の土を一部取り除いてパーライトという黒曜石をいれた。石は細かく水の通りは良さそうだが、結局粘土層があるのでそこから先は同じかもしれない。試すのが大事なので、まずはやってみた。


2018年4月7日
一番北側でがんばっていた大根が終了したので、その地下にコンポスト容器で作った籾殻堆肥をすき込んだ。1本でちょうど1畝分で終わった。もう1個あるが
その分は、一番南側の今玉ねぎが植わっている箇所に、終わったらすき込む予定。
2018年2月3日
ブロッコリーが完了したので、土づくり。2列の畝を掘り、下から発酵鶏糞、籾殻、油かす、ブロッコリー・白菜の外葉、米ぬか、落ち葉、発酵鶏糞の順で積み重ね、最後に土をかけて水をまいた。籾殻堆肥を土の中で発酵成熟させようという試み。

2018年1月14日
キャベツが完了したので、その場所に2列の畝を掘り、下から牛糞堆肥、籾殻、油かす、キャベツ・白菜の外葉、米ぬかの順で積み重ね、最後に土をかけて水をまいた。キャベツ・白菜の外葉は、生ゴミ堆肥のつもり。このまま、じっくり熟成させて夏野菜の仕込みの5月まで放置する予定。
2017年12月16日
籾殻堆肥をコンポスト容器2つで発酵させようと1ヶ月前から取り組んでいるが、まだ籾殻と藁がたくさん残っているので、土に埋めて堆肥化をはかることにした。空いている畝をつぶして耕し、3列の穴を掘った。下から、牛糞堆肥、籾殻、藁、腐葉土、米ぬかの順で積み重ね、最後に土をかけて水をまいた。やっていることはコンポスト容器とほぼ同じ。容器を使って上に積み上げるか、掘った穴を使って下へと重ねるかの違いだけ。来年の夏野菜の仕込みには穴を掘り起こして、肥料として畑にばらまく予定。それまでは、じっくりゆっくり熟成するのをじっと待つ。 ※真ん中の畝の中程に粘土質の土層あり

2017年12月9日
仕込んでから約1ヶ月、嫌なにおいもカビもないので、撹拌してみることに。小さめのスコップでかき回したが半分から下は、スコップが入らず、上部をかき混ぜた程度。水分が少し足りないようなので、明日水分を補給する予定。
2017年12月3日
3週間が経過、白カビが少々。容器の中が暖かい感じ。最上部に米ぬかを追加、その上から土をかぶせた。下層の状態は見えないので不明。1ヶ月後には、スコップを入れて中をかき混ぜようと思う。
2017年11月19日
1週間後の今日は、特に変化なし。
2017年11月12日
去年から取り組んでいる粘土質の土壌改良に使うため、友人から籾殻と藁を大量にいただいた。作物が少ない冬を利用して籾殻主体の完熟堆肥をつくって春夏野菜の仕込みの時期(4月頃)に畑全体に撒く予定。今年はコンポスト容器を入手したので、それを利用してサンドイッチ状に層を作って発酵・堆肥化を待つ。下から籾殻、米ぬか、鶏糞、油かす、籾殻、米ぬか、鶏糞、腐葉土、籾殻、油かすと重ねて、水を多めにかけてふたをするだけ。発酵促進剤とかも有るようだけど、自然発酵にこだわるので薬品は使わず、発酵材は米ぬかや鶏糞に担ってもらう考えだ。約半年後には、栄養ある堆肥に変身して作物の成長を助けてほしい。


2017年9月9日
コンポスト容器を東区役所に受け取りにいった。本来生ゴミ堆肥をつくる容器だが、今年も友人からいただける籾殻を堆肥化しようと考えている。それに使う予定。
2017年8月5日
今年も籾殻をいただけそうなので、籾殻堆肥づくりに挑戦する予定。「土耕菌ナルナル」という発酵促進剤があるらしい。籾殻と米ぬかと鶏糞と発酵促進剤と水を使って作る堆肥。粘土質をすこしでも解消するために今年も挑戦だ。http://narunaru.shop-pro.jp
2017年7月16日
昨日の15日に平鍬の柄が根元で折れてしまった。父親から引き継いだので、使用期間は不明だが相当年季が入っているのは外観から想像がつく。折れたものはしょうがない。平鍬がないと何も始まらないので急遽「農家の店しんしん」へ直行。ホームセンターでも以前に見たが、品揃えの数ではしんしんが一番。今のサイズ感がちょうどいいので、一番近いサイズのを選択。税抜き4900円。道具はピンキリ有るので使ってみなければ価値はわからない。もっと安いのも有ったが道具は金額に比例するので高い方を選んだ。早速使ってみたが、いい感じ。違和感もなく今までと同じ感覚で使いやすい。大事にしよう。

4月22日
穴掘りの完熟堆肥作成は、とりあえずここで完了。穴の中の肥えた土を畑全体に分散した。特に大根のあとは何も栄養を与えてないので、そこを重点的に耕した。
4月15日
定期的に空気のを入れた方がいいとのことなので、毎週末スコップをいれて土の掘り返しを行っている。厳密には土というより、積み上げた堆肥を混ぜていると言った方が正しい。
3月5日
白カビが生えてきた。完熟にむけて順調だ。白カビは生えた方がいいらしい。毎週スコップで返して空気の入れ換えを行っている。堆肥として使えるように毎週の手入れが楽しみだ。
1月22日
籾殻があるので、堆肥づくりを行うことにした。発酵させて完熟堆肥を作るのが目標だがノウハウも道具も何もない。普通は容器や木枠のなかに積み上げて、上からブルーシートをかぶせ半年くらい寝かせるようだが、その容器すらないので穴を掘って重ねることにする。直径1メートル、深さ50cmくらいの穴を掘り、下から籾殻、米ぬか、落ち葉、牛糞、鶏糞をいれて最後に上から水と土をかけてブルーシートをかぶせた。時々かき混ぜる方がいいとのこと。来週やってみよう。1月8日の写真と同じに見えるが、8日のはまんべんなく畑の土にすき込んだが、今回は穴に積み重ねた。

1月8日
残りの北側面も、土作りを施行。完熟牛糞堆肥、籾殻、油かす、米ぬかは昨日と同じだが、腐葉土は落ち葉に変えた。理由は節約。ただで拾ってきた落ち葉でもいけそうなのでそうしてみた。畑にすき込んでも落ち葉は大きく原型をとどめているので目立つ。数ヶ月もすれば腐って土に帰るのだろうか?

1月7日
2017年初めての書き込み。今年から新しい記事を上に書くようにした。本当は1記事1枚が普通だけど、一つの野菜の時系列での成長ぶりが重要なので、今年も1野菜1ページで野菜の育つ変化をわかりやすく書きたい。
南側反面の地質改良に着手。脇芽がまだ期待できるブロッコリーを片付けて、完熟牛糞堆肥、籾殻、腐葉土、油かす、米ぬかをすき込んだ。特に籾殻は排水性の向上に好影響があるとのこと。多めに入れてみた。鍬で耕すこと3回。ふかふかの土になった。ただこれがいつまで持つのか?雨が降ったらどうなるのか?籾殻は完全に分解するのに1年以上掛かるということだが、野菜の植え付けに障害がないのか?まだまだ課題は多いが、まずは想定通りにスタート。
12月30日
冬の間の休耕期間を利用して、土質改良を試みてみよう。
空いたジャガイモと黒豆の場所を利用して、いただいたもみ殻堆肥づくりをした。太めで深めの溝を掘り下から落ち葉、もみ殻、米ぬか、もみ殻、バーク堆肥、発酵牛糞、もみ殻、油かす、コーランネオ、もみ殻を溝に入れて積層構造で、水やり。全部で10層以上は重ねたと思う。最後に、土を戻して鎮圧のため踏み固める。これが大事。全体重をかけると、かなり沈む。雨が降った後に、黒マルチをかける予定。昨年まではコンポスト容器でやっていた作業だが今年は籾殻の量と畑の空き具合から、容器は止めて、土の中で発酵させることにした。籾殻はそのままでは肥料にならず、発酵させる必要がある。
2020年11月8日
今日友人から藁と籾殻1袋をいただいた。毎年恒例のもみ殻堆肥づくりをする予定。今は場所が無いので、このままの状態で保留継続。

2020年1月25日
今日白菜が片付いたので、畝を使ったもみ殻堆肥づくりをした。もみ羅、鶏糞、米ぬか、落ち葉、白菜の残菜、コーランネオ半袋を順に重ねて、水やりして土を戻してしっかり鎮圧した。土を肥やすのと、籾殻を土になじませるのが目的。コンポスト容器も同じ。本当は1年くらい置きたいが、狭い畑では、そうはいかない。

2019年12月15日
一番南側のキャベツが片付いたので、2回目のもみ殻堆肥づくり。先週と同様に溝を掘り、もみ羅、鶏糞、米ぬか、油かす、キャベツの残菜、コーランネオ半袋を混ぜて、最後にたっぷり水やりして土を戻してしっかり鎮圧した。

2019年12月7日
容器が一杯だから、土の溝を利用して、もみ殻堆肥づくりを。一番北側の黒豆の収穫後、太め深めの溝を掘り下から落ち葉、もみ殻、米ぬか、わら、発酵鶏糞、油かす、コーランネオを畝全体に入れて混ぜて、水やり。まるで残渣ゴミの詰め合わせ。その後、土で蓋をして鎮圧のため何度も往復して踏み固める。これが大事。全体重をかけると、かなり沈む。このままでは作物が倒れるわけだ。雨が降った後に、黒マルチをかける予定。来年の春までに発酵した籾殻ができる?

2019年11月20日
水を追加。中の温度が上がっているようだ。発酵の兆候か?重石を3つほど入れた。1ヶ月くらいは放置の予定。
2019年11月16日
もみ殻堆肥発酵に「コーランネオ」という発酵促進剤を購入したので、もう一つのコンポスト容器もやる事にした。下の土を鍬で柔らかく耕した。その上に
もみ殻、発酵鶏糞、もみ殻、米ぬか、コーランネオ、もみ殻、油かす、コーランネオ、もみ殻、土の順で積み上げた。途中で水を大量に入れ、靴の裏で圧縮した。結構体積が下がる。さらに同じ事を繰り返す。途中黒大豆の枯れ葉も投入。コーランネオの採用も初めてだが、靴で圧縮したのは発酵に効果がありそう。
2019年11月10日
コンポスト容器を使ってのもみ殻堆肥発酵に一つだけ挑む事にした。下からもみ殻、発酵鶏糞、もみ殻、米ぬか、もみ殻、発酵牛糞を2回通り入れて水を多めにかけて終了。今年は初めて「発酵促進剤」なるものを使うことにした。「コーランネオ」という商品をジャンボエンチョーで購入。すでに階層を積み上げた後なので、スコップで掘りながら途中に入れた。最上部にも全体にまぶして、最後に土をかぶせた。はじめから使えば良かった。上手に発酵するかは、これからのお楽しみ。


2019年11月2日
同級生の農家さんから藁ともみ殻をいただいた。藁は来年の4月仕込みの春夏野菜につかう。もみ殻は、今年の秋冬野菜が終わる年明け早々に、空いた畝を使い発酵堆肥を作る予定。毎年コンポスト容器を使っているが今年は畑の畝を使う予定。もみ殻だけでも地質改良になるのだが、4ヶ月発酵させると立派な堆肥になる。

2019年4月21日
夏野菜に向けて、土づくりをした。先週、牛糞堆肥、油かす、米ぬか等を蒔いて耕した。今週は、石灰を蒔いて酸性度を中和した。先輩農家から苦土石灰より有機カキ殻石灰がいいと聞いたので、はじめて使ってみた。苦土よりやや多い量を蒔いた。20kg入りしかなかったので、かなり余ってしまった。使用量の目安は、4×5メートルの面積に約2Kgくらいなので、10分の1しか使わない計算だ。2週間後の5月4日ごろに夏野菜を仕込む予定。
また石灰購入でジャンボエンチョー染地台店に行ったら、連作障害防止の「菌の黒汁」入りのバーク堆肥を見つけたので思わず3袋も買ってしまった。1袋約500円。一緒に蒔いて耕した。苦い経験があるので、連作障害防止の文句にはめっぽう弱い。

2019年3月31日
キャベツ・ブロッコリーが終了し、北側端の玉ねぎと南側端の春ジャガ以外はすべて空いたので、コンポスト容器で作った籾殻堆肥をすき込んだ。容器一個分ではやや足りないので、残りは2個目の一部を来週作業する予定。さらに残りは、今の玉ねぎが終わったらすき込む予定。
今年の反省点として、水が少ない、攪拌ができていないため、牛糞堆肥や米ぬかが固まってしまった。来年からは土の下に入れて発酵させようと思う。牛糞堆肥とバーク堆肥で籾殻をサンドする方法がいいようだ。
2018年12月2日
籾殻堆肥を使った土壌改良(その2)を施した。容器がもうないので、空いた畝を使って同様の効果を狙う。黒豆が予定より早く空いたので、その畝2列に溝を深く掘り、そこに下から籾殻、発酵鶏糞、籾殻、米ぬか、油かす、籾殻、鶏糞、米ぬかと重ねた。途中で水を加え、土を被せた跡は何回も踏み土をしながら畝を往復した。それぞれが密着するように、圧縮した。コンポスト容器の時は、2個で籾殻1袋を使い切ったが、今回はけっこう余った。今週は雨が多そうなので、ちょうどいい。このまま4月下旬まで放置(土中では籾殻の発酵がすすみ堆肥として熟成されるはず)し、その後他の場所へ籾殻を振り分け、すき込む。

2018年11月18日
コンポスト容器を使った土壌改良に今年も挑戦してみることに。籾殻主体の完熟堆肥をつくって春夏野菜の仕込みの前(4月頃)に畑全体にすき込む予定。容器にサンドイッチ状に層を作って発酵・熟成・堆肥化を待つ。下から籾殻、発酵鶏糞、籾殻、米ぬか、油かす、籾殻、米ぬか、鶏糞、籾殻、腐葉土、籾殻、油かすと重ねた。2層くらい積み上げて足で踏んで圧縮し、水をかけての繰り返し。発酵促進剤は使わず、発酵剤は米ぬかや鶏糞に担ってもらう考えだ。約半年後には、完熟堆肥が完成。毎年、これを繰り返していけば、粘土質からの土壌改良にも役立つだろう。籾殻は水の通りがいいので排水性も高いはずだ。容器だけでは籾殻が半分以上余るので、空いた畑を掘り、その穴に同じように積み重ねて最後に土と水をかけて半年置いて熟成を待つ。

2018年10月6日
じゃがいも、大根といった冬野菜の準備中に粘土質の層を発見して、その修復作業にかなりの時間と費用を費やした。ひたすら黄茶色の粘土質の土を取り除き、その分の補充として「矢作砂(中粒)」とかバーク堆肥とかを入れた。矢作砂はこれまで合計10袋くらい買っているんじゃないかな?キャベツ、じゃがいも、大根の一部に使っている。今日も大根の土づくりの途中でまた出てきたので、削除と補充で明け暮れた。

2018年9月2日
夏野菜を片付けた。豪雨のたびに雨水が池のように貯まる西側の真ん中部分を掘りこんだ。案の定、途中から粘土質の黄茶の土が出てきた。粘土土を取り除いて減った分「パーライト」という黒曜石を補充する水はけ改良作戦を決行。掘っては取り除く作業を延々と決行。それが3カ所ほどあり、かなりの粘土土を取り除いた。といっても全体からすればごくわずか。パーライトが足らなくなったので、増し土2袋を購入(1袋25リットル/1袋400円ケーヨーD2)。
これで水はけがどの程度変わるか、まずは様子をみよう。

2018年5月27日
2つめのコンポスト容器で作った籾殻堆肥を、玉ねぎの収穫後にすき込んだ。
また、南側の畝の西側は排水が特に悪く、大雨の次の日には池ができる状態だ。地下の粘土質の土が原因と思う。地下の粘土質の土を一部取り除いてパーライトという黒曜石をいれた。石は細かく水の通りは良さそうだが、結局粘土層があるのでそこから先は同じかもしれない。試すのが大事なので、まずはやってみた。


2018年4月7日
一番北側でがんばっていた大根が終了したので、その地下にコンポスト容器で作った籾殻堆肥をすき込んだ。1本でちょうど1畝分で終わった。もう1個あるが
その分は、一番南側の今玉ねぎが植わっている箇所に、終わったらすき込む予定。
2018年2月3日
ブロッコリーが完了したので、土づくり。2列の畝を掘り、下から発酵鶏糞、籾殻、油かす、ブロッコリー・白菜の外葉、米ぬか、落ち葉、発酵鶏糞の順で積み重ね、最後に土をかけて水をまいた。籾殻堆肥を土の中で発酵成熟させようという試み。

2018年1月14日
キャベツが完了したので、その場所に2列の畝を掘り、下から牛糞堆肥、籾殻、油かす、キャベツ・白菜の外葉、米ぬかの順で積み重ね、最後に土をかけて水をまいた。キャベツ・白菜の外葉は、生ゴミ堆肥のつもり。このまま、じっくり熟成させて夏野菜の仕込みの5月まで放置する予定。
2017年12月16日
籾殻堆肥をコンポスト容器2つで発酵させようと1ヶ月前から取り組んでいるが、まだ籾殻と藁がたくさん残っているので、土に埋めて堆肥化をはかることにした。空いている畝をつぶして耕し、3列の穴を掘った。下から、牛糞堆肥、籾殻、藁、腐葉土、米ぬかの順で積み重ね、最後に土をかけて水をまいた。やっていることはコンポスト容器とほぼ同じ。容器を使って上に積み上げるか、掘った穴を使って下へと重ねるかの違いだけ。来年の夏野菜の仕込みには穴を掘り起こして、肥料として畑にばらまく予定。それまでは、じっくりゆっくり熟成するのをじっと待つ。 ※真ん中の畝の中程に粘土質の土層あり

2017年12月9日
仕込んでから約1ヶ月、嫌なにおいもカビもないので、撹拌してみることに。小さめのスコップでかき回したが半分から下は、スコップが入らず、上部をかき混ぜた程度。水分が少し足りないようなので、明日水分を補給する予定。
2017年12月3日
3週間が経過、白カビが少々。容器の中が暖かい感じ。最上部に米ぬかを追加、その上から土をかぶせた。下層の状態は見えないので不明。1ヶ月後には、スコップを入れて中をかき混ぜようと思う。

2017年11月19日
1週間後の今日は、特に変化なし。
2017年11月12日
去年から取り組んでいる粘土質の土壌改良に使うため、友人から籾殻と藁を大量にいただいた。作物が少ない冬を利用して籾殻主体の完熟堆肥をつくって春夏野菜の仕込みの時期(4月頃)に畑全体に撒く予定。今年はコンポスト容器を入手したので、それを利用してサンドイッチ状に層を作って発酵・堆肥化を待つ。下から籾殻、米ぬか、鶏糞、油かす、籾殻、米ぬか、鶏糞、腐葉土、籾殻、油かすと重ねて、水を多めにかけてふたをするだけ。発酵促進剤とかも有るようだけど、自然発酵にこだわるので薬品は使わず、発酵材は米ぬかや鶏糞に担ってもらう考えだ。約半年後には、栄養ある堆肥に変身して作物の成長を助けてほしい。


2017年9月9日
コンポスト容器を東区役所に受け取りにいった。本来生ゴミ堆肥をつくる容器だが、今年も友人からいただける籾殻を堆肥化しようと考えている。それに使う予定。
2017年8月5日
今年も籾殻をいただけそうなので、籾殻堆肥づくりに挑戦する予定。「土耕菌ナルナル」という発酵促進剤があるらしい。籾殻と米ぬかと鶏糞と発酵促進剤と水を使って作る堆肥。粘土質をすこしでも解消するために今年も挑戦だ。http://narunaru.shop-pro.jp
2017年7月16日
昨日の15日に平鍬の柄が根元で折れてしまった。父親から引き継いだので、使用期間は不明だが相当年季が入っているのは外観から想像がつく。折れたものはしょうがない。平鍬がないと何も始まらないので急遽「農家の店しんしん」へ直行。ホームセンターでも以前に見たが、品揃えの数ではしんしんが一番。今のサイズ感がちょうどいいので、一番近いサイズのを選択。税抜き4900円。道具はピンキリ有るので使ってみなければ価値はわからない。もっと安いのも有ったが道具は金額に比例するので高い方を選んだ。早速使ってみたが、いい感じ。違和感もなく今までと同じ感覚で使いやすい。大事にしよう。

4月22日
穴掘りの完熟堆肥作成は、とりあえずここで完了。穴の中の肥えた土を畑全体に分散した。特に大根のあとは何も栄養を与えてないので、そこを重点的に耕した。
4月15日
定期的に空気のを入れた方がいいとのことなので、毎週末スコップをいれて土の掘り返しを行っている。厳密には土というより、積み上げた堆肥を混ぜていると言った方が正しい。
3月5日
白カビが生えてきた。完熟にむけて順調だ。白カビは生えた方がいいらしい。毎週スコップで返して空気の入れ換えを行っている。堆肥として使えるように毎週の手入れが楽しみだ。
1月22日
籾殻があるので、堆肥づくりを行うことにした。発酵させて完熟堆肥を作るのが目標だがノウハウも道具も何もない。普通は容器や木枠のなかに積み上げて、上からブルーシートをかぶせ半年くらい寝かせるようだが、その容器すらないので穴を掘って重ねることにする。直径1メートル、深さ50cmくらいの穴を掘り、下から籾殻、米ぬか、落ち葉、牛糞、鶏糞をいれて最後に上から水と土をかけてブルーシートをかぶせた。時々かき混ぜる方がいいとのこと。来週やってみよう。1月8日の写真と同じに見えるが、8日のはまんべんなく畑の土にすき込んだが、今回は穴に積み重ねた。

1月8日
残りの北側面も、土作りを施行。完熟牛糞堆肥、籾殻、油かす、米ぬかは昨日と同じだが、腐葉土は落ち葉に変えた。理由は節約。ただで拾ってきた落ち葉でもいけそうなのでそうしてみた。畑にすき込んでも落ち葉は大きく原型をとどめているので目立つ。数ヶ月もすれば腐って土に帰るのだろうか?

1月7日
2017年初めての書き込み。今年から新しい記事を上に書くようにした。本当は1記事1枚が普通だけど、一つの野菜の時系列での成長ぶりが重要なので、今年も1野菜1ページで野菜の育つ変化をわかりやすく書きたい。
南側反面の地質改良に着手。脇芽がまだ期待できるブロッコリーを片付けて、完熟牛糞堆肥、籾殻、腐葉土、油かす、米ぬかをすき込んだ。特に籾殻は排水性の向上に好影響があるとのこと。多めに入れてみた。鍬で耕すこと3回。ふかふかの土になった。ただこれがいつまで持つのか?雨が降ったらどうなるのか?籾殻は完全に分解するのに1年以上掛かるということだが、野菜の植え付けに障害がないのか?まだまだ課題は多いが、まずは想定通りにスタート。
12月30日
冬の間の休耕期間を利用して、土質改良を試みてみよう。